
Last update April 5, 2017


かって製材所があった…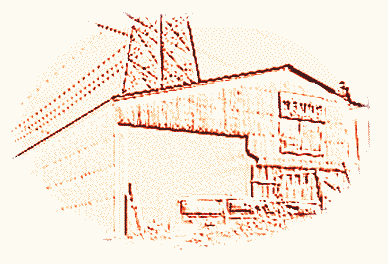 2014年4月1日午前4時
2014年4月1日午前4時 そんなわけで、私の物心ついた頃から、ここには製材所があった。その昔は大きな水車があったらしい。中学生になって、確か「メッケン」とかいうあだ名の社会科の先生(申し訳ないが名前は覚えていない)が「そこは昔、大きな水車があったんぞ」と教えてくれた。それ以外にも、「郷土史」だったかは定かではないが、何かの研究調査をしている人が「ここには大きな水車があったらしいんですが、その水車、今はどこにありますか?」と、家に訪ねて来たこともあったらしい。まさに「かって水車があった…」というわけで、それがどうなったのか、子供心にも興味があったが、主に聞いても納得できる答えは得られなかった。おそらく(というかそれしかないが)、木を切るのに水車の動力を利用していたのだろう。
そんなわけで、私の物心ついた頃から、ここには製材所があった。その昔は大きな水車があったらしい。中学生になって、確か「メッケン」とかいうあだ名の社会科の先生(申し訳ないが名前は覚えていない)が「そこは昔、大きな水車があったんぞ」と教えてくれた。それ以外にも、「郷土史」だったかは定かではないが、何かの研究調査をしている人が「ここには大きな水車があったらしいんですが、その水車、今はどこにありますか?」と、家に訪ねて来たこともあったらしい。まさに「かって水車があった…」というわけで、それがどうなったのか、子供心にも興味があったが、主に聞いても納得できる答えは得られなかった。おそらく(というかそれしかないが)、木を切るのに水車の動力を利用していたのだろう。 ともかく、物心ついた頃から製材所があったわけで、小学校のときのお絵かきの宿題で、回転する円形ノコギリを挟んで二人がかりで丸太を切る「働くおとーさん」を描いたような記憶がある。その頃の製材所は、1976年の火事に遭遇する前だったので、道路に面した場所に機械が移動するレールが敷かれてあった。レールの回りは一段高くなった板張りの床で囲まれ、作業員が行き来できるようになっていた。道路から離れたところのスペースでは、製材後の廃材を風呂炊き用の薪に加工し、針金の輪っかを使って結わえる作業が行われていた。工場では、材木を切り出すときのウィンウィンと回転するノコの音もさることながら、主をはじめ、近所のおいちゃんやおばちゃんたちもそこで働いていて、活気に溢れ、機械のオイルの臭いがした。
ともかく、物心ついた頃から製材所があったわけで、小学校のときのお絵かきの宿題で、回転する円形ノコギリを挟んで二人がかりで丸太を切る「働くおとーさん」を描いたような記憶がある。その頃の製材所は、1976年の火事に遭遇する前だったので、道路に面した場所に機械が移動するレールが敷かれてあった。レールの回りは一段高くなった板張りの床で囲まれ、作業員が行き来できるようになっていた。道路から離れたところのスペースでは、製材後の廃材を風呂炊き用の薪に加工し、針金の輪っかを使って結わえる作業が行われていた。工場では、材木を切り出すときのウィンウィンと回転するノコの音もさることながら、主をはじめ、近所のおいちゃんやおばちゃんたちもそこで働いていて、活気に溢れ、機械のオイルの臭いがした。 それから年月が経ち、いくつかの災難が押し寄せた。前述のように、火事もあった。このときは、ノコをはじめいろんな器具が保管されていて、子供にとっては探検ごっこの世界だった工場の二階も、年に二度の楽しみだった臼と杵を使っての餅つきが行われた土間も焼けた。製品もすべて焼けた。しかし、建物を立て替え、工場のレイアウトは変わったが、製材所は無くならなかった。その後も材木を作り続けた。金融的な事故もあって、おいちゃんやおばちゃんたちは働きに来なくなり、主とその妻だけの製材業になったが、それでも製材所は無くならなかった。細々と製材し続けた。
それから年月が経ち、いくつかの災難が押し寄せた。前述のように、火事もあった。このときは、ノコをはじめいろんな器具が保管されていて、子供にとっては探検ごっこの世界だった工場の二階も、年に二度の楽しみだった臼と杵を使っての餅つきが行われた土間も焼けた。製品もすべて焼けた。しかし、建物を立て替え、工場のレイアウトは変わったが、製材所は無くならなかった。その後も材木を作り続けた。金融的な事故もあって、おいちゃんやおばちゃんたちは働きに来なくなり、主とその妻だけの製材業になったが、それでも製材所は無くならなかった。細々と製材し続けた。そうして、さらに幾星霜。主も後期高齢者となり、製材の仕事も来なくなった。しかし、製材所はまだそこにあり、昔からそうであったように、そこが唯一の居場所であったかのように、主は毎日、一日中そこで過ごした。おそらく、暑い日は、工場を駆け抜ける涼風に吹かれながら、寒い日は、車の中でぽかぽかと暖かい冬の陽射しを浴びながら…。何を考えていたのか、それとも何も考えていなかったのか、それはわからない。ともかく製材所はあった。主とともにそのまま存在し続けた。 数年後、主は旅立った。しかし、製材所は残った。もう二度と機械のボタンを押し、ノコを回す者もいない。それでも製材所は無くならなかった。 それから二年経ったある秋の日のこと。竜巻のような大きな台風がやって来た。一瞬のうちに工場の屋根が飛び、建物が崩壊した。製材所は無くなった。主の後を追うように、永遠に姿を消すことになったのである。  |

