レコーディングあれこれ 先日久しぶりに英語ナレーションに立ち会った。ある企業の英語版ビデオを制作するということでネイティブ・ナレーターによるナレーションの吹き込みを行ったわけである。通常、日本企業の場合、まず日本語版を制作する。そしてそれをもとに英語版の制作となる。私見(理想)を言えば、英語版は英語の発想で一から作り直すくらいの思い切りが必要かもしれないが、予算の関係もあり、日本の企業ではほとんど行われることはない。たまに英語版しか作らないことが最初からわかっていても、まず日本語でシナリオを作成する。まず日本人担当者が理解できる「日本語」で、ということだろう。後で「英語だったからよくわからなかったが、適切ではない情報が含まれていた」などという問題が起きても困るので、制作を請け負う側としても、まず日本語でOKを出していただいたほうが安心でもある。
先日久しぶりに英語ナレーションに立ち会った。ある企業の英語版ビデオを制作するということでネイティブ・ナレーターによるナレーションの吹き込みを行ったわけである。通常、日本企業の場合、まず日本語版を制作する。そしてそれをもとに英語版の制作となる。私見(理想)を言えば、英語版は英語の発想で一から作り直すくらいの思い切りが必要かもしれないが、予算の関係もあり、日本の企業ではほとんど行われることはない。たまに英語版しか作らないことが最初からわかっていても、まず日本語でシナリオを作成する。まず日本人担当者が理解できる「日本語」で、ということだろう。後で「英語だったからよくわからなかったが、適切ではない情報が含まれていた」などという問題が起きても困るので、制作を請け負う側としても、まず日本語でOKを出していただいたほうが安心でもある。ということで、日本語シナリオライターがシナリオ原案を担当する。クライアントのほうで最終OKが出た時点で英語シナリオの作成にかかる。もちろん日本語をベースとするので「翻訳」となるが、できるだけ英語のロジックや発想で書かれたものに近づけるため情報ごとの「再構築」となる。単語や文章レベルの翻訳ではなく、情報を整理、選択していく「構造的な翻訳」であり、勝手に言わせてもらえば「超翻訳」というところ。とはいえ、企業さん相手なのであまり原文の情報から離れてはいけない。人の名前にしても「太郎さん」が「Tom」にはならないし、「彼女は留袖を着ていた」という場合(企業向けのものにはまず無いとは思うが)、 "She was in a gorgeous evening dress." というわけにもいかないだろう。が、たぶん、状況によっては "a formal dress" くらいにはなるかもしれない。というのも "tomesode, a formal kimono" などというよりは、英語圏の人にはすんなり受け入れてもらえるからだ。あくまでこれは「留袖」が全体の文脈においてさほど重要でない場合に限るわけで、たとえば「日本の着物紹介」といったテーマのものであれば話は違ってくる。 じゃあどこからどこまでがOKで、どこからがダメなのか、というとそんなルールはない。置かれている状況やあらゆる要素を考慮に入れながら、その都度判断していくことになる。えらい大変な仕事やなあ… ということになるが、実はこの部分が一番楽しい部分かもしれない。特に企業の場合は「つかず離れず」の振れ幅をどう調整していくかがポイントである。うまく行けば「よく情報のコアを捉えてアクティブな表現にしてくださってますね。」ということになるし、間違えば「日本語と全然違う!勝手に内容変えるなんて、何考えてんねん!!!」というお叱りをいただくことになる。何年やっていても、提出するたびに「離れすぎていないか」とドキドキしてしまう、トキメキの瞬間なのだ。提出する前にはもちろんネイティブチェックを通す。英語が母国語でない限り、これは絶対に必要な作業である。言ってみれば印籠やお墨付きと同じで、保険のようなものとも言えるかもしれない。何か英語的に問題が起きたときに「いや、いちおうネイティブにはチェックしてもらってますけどー」と言えるためのものである。 話を戻してレコーディング。制作関連スタッフはもちろん、クライアントの担当者も立ち会うのが普通である。現場でナレーションの内容が変わることもしょっちゅうだ。映像に比べてナレーションが長すぎてこぼれてしまう場合や、クライアント担当者の意見で「やっぱりここはこうしてくれ」とか「気が変わった」とかいう場合もある。いずれにしても「現場対応」である。他のスタッフや担当者の「まだか、まだか」という催促モード視線に見守られながら、ナレーターと話し合い、文章を削ったり、書き直したりする。ひどいときには、現場で数ページの追加原稿を訳したこともある(そのときのナレーターがたまたま中学時代に見ていたNHKの英語番組のイギリス人講師だったりして感激!)。ともあれ、限られた時間でどこまで対応できるかという「度胸と賭け(?)」の状況におけるこの「現場対応」、スリルとサスペンスがあり、パニック映画の主人公になったような気分になれる。 今回は残念ながら(?)、そういったハプニングもなく、つつがなく終了した。オーストラリア人の女性ナレーターだったが、とても陽気な彼女は普段は会話学校の英語講師をしているということ。本国ではレポーターの仕事をしていたそうだ。その日は追加変更などもなくすんなり終ってしまったが、ナレーション立会いでいつも感じるのは、「現場」の緊張感とナレーターや自分を含むスタッフ全員の一体感の素晴らしさである。映像と音楽がスタジオいっぱいに流れるなか、自分の訳した文章をナレーターが思いをこめて読み込む… チームワークによってモノづくりが確かに行われている、そしてその一部に自分がいるということの実感。みんなの力でひとつの良いものが出来ていくという感動。まさにこの仕事をやっていて良かったと思う至福の瞬間だ。そして、そんな瞬間をこれからも重ねていきたいと思う今日この頃である。 |
|
|
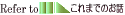 |










