
|
| スペイン語の受動態の考え方3 |
歴史的考察
上の説明で、スペイン語にはそもそも純粋な「受身形」というものがあるのかということが問題になってきましたが、言い換えれば、「あるような、ないような」というのがスペイン語の受身形なのかもしれません。スペイン語の親であるラテン語の受身形を見てみると、なるほどとうなづけるものがあります。スペイン語の「
ところが、もともとラテン語には、複合形ではなく、
つまり、こういった語尾変化に基づくラテン語の「受身形」や再帰代名詞を使った表現には、「受身」以外の用例が多く含まれていたというわけで、いわゆる中間態(
次に、再帰代名詞
さらに、スペイン語は能動的視点を持っているため、行動主を主語とした文章表現が基本です。よって、行動主を言及したくない、行動主がわからないという場合にのみ、「受身」が使われていたのですが、それは受動主が3人称の場合のみに限られていました。第三者のことについては、「誰が行為を行ったか」といった経緯がわからない(問題にしない)ということは十分起こりうるので、これも当然といえば当然のことかもしれません。
というわけで、
こうしてみると、この文型であれば必ず受動態といった明快な図式が成り立たないのがラテン語の受身形であり、スペイン語特有の
また、受身表現の文型も受身以外の用例を持っているため、「能動態 vs 受動態」ではなく、「能動態 vs 非能動態」という対比を用いて「態」というものを捉えたほうがわかりやすいかもしれません。「能動態 vs 非能動態」とは、言い換えれば、「視点が行動主にあるか」(能動態)、「行動主からそれているか」(非能動態)ということに他なりません。行動主を主語にする場合は能動態であり、行動主を主語にしない(ぼかす、受動主を主語にする)場合が非能動態というわけです。
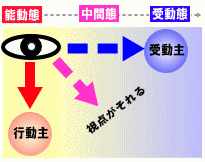
ですから、スペイン語では、「これが受身だ!」といった明確な区分けがあるというよりも、「能動態であるか、能動態でないか」という対比があり、「能動態でない」表現のなかに一部として含まれるのが「受身」表現であると理解するほうがより適切ではないかと思われます。










