翻訳ビジネス事情 翻訳というのははっきり言って企業のビジネスとしては成立しにくい仕事である。とくに、「質の高い翻訳」を提供しようとすればビジネスにはならない。企業として採算が取れないからである。というわけで、翻訳会社でも純粋に「翻訳」だけで食べているところは少ないのではないかと思われる。事実、筆者の知っている翻訳会社でも、翻訳や通訳の学校を経営したり、会議通訳なども手がけたり、あるいは、DTP(レイアウト)も込みで受注するということを同時に行っている。学校を経営している場合は、当然、生徒のなかから優秀な人材を自社お抱えの翻訳家として使うわけであり、「卒業したらお仕事を依頼します」というのを「売り」にしているわけである。まあ、うまいやり方だと思う。一方、翻訳オンリーで食べて行けるところというのは、よほど経営的な智恵があるか、薄利多売で見るも無残な質のものを出しているかのどちらかである。
翻訳というのははっきり言って企業のビジネスとしては成立しにくい仕事である。とくに、「質の高い翻訳」を提供しようとすればビジネスにはならない。企業として採算が取れないからである。というわけで、翻訳会社でも純粋に「翻訳」だけで食べているところは少ないのではないかと思われる。事実、筆者の知っている翻訳会社でも、翻訳や通訳の学校を経営したり、会議通訳なども手がけたり、あるいは、DTP(レイアウト)も込みで受注するということを同時に行っている。学校を経営している場合は、当然、生徒のなかから優秀な人材を自社お抱えの翻訳家として使うわけであり、「卒業したらお仕事を依頼します」というのを「売り」にしているわけである。まあ、うまいやり方だと思う。一方、翻訳オンリーで食べて行けるところというのは、よほど経営的な智恵があるか、薄利多売で見るも無残な質のものを出しているかのどちらかである。実際、自動翻訳ソフトなどを使ってまず機械翻訳をやり、それを手直しするという方法で「翻訳」を行っているところもあるという話だ。それでいて、「弊社は質の高い翻訳を提供します」と言っていたりする。もっとも、「弊社の翻訳は安い代わりに品質は高くありません」などと正直に言うような会社はいないが、よほど優れた自社開発の翻訳ソフトを持っているのか(日英間でそんなものがあればまさに時代の大発明である)、手直しのノウハウがこれまた社外秘の大革新に値するような優れたものなのか、手直しするチェッカーが超人であるかのいずれかだとしか思えない。たとえアタマが固いと言われようが、石器時代の精神と言われようが、筆者には信じられないことである。翻訳サンプルを見せてもらっても、申し訳ないのだが筆者にはそれが「高品質」だとはどうしても思えなかったりする。 事実、以前に手がけた翻訳業務のなかで、それらしき成果物を見せられた経験がある。この仕事は、納期も予算的にも非常に厳しく、しかも内容的にもむずかしく、翻訳量も多いという状況があり、自分ひとりでは物理的にやりきれるものでもなかったため翻訳会社にも依頼した。そういう厳しい状況のなかで、質の良い翻訳者の数にも限りがあり、先方としても苦肉の策だったのかもしれない。依頼した翻訳のすべてがそういうわけではなかったが、誰が見ても意味不明と思われるアウトプット群があった。よく見るとその一連の部分だけ、随所に不自然さが感じられ、翻訳者が内容を理解せずにただ翻訳先言語に移し変えているだけというのがありありとわかるのである。 まさに「暗号」のようである。こういった翻訳先言語を用いた「暗号化」は、自動翻訳ソフトなどが得意な分野(?)である。ターゲット言語にはなっているのに、なぜか意味がわからないという不思議なミステリー現象である。「ミステリー」などと言うと大げさだが、担当している翻訳者(あるいは手直し担当者)にとっても何が書いてあるのか「ミステリー」だったに違いない。しかし、ミステリー劇場などというのは、解決の糸口をいろいろと見せてくれるし、探偵などがちゃんといて、最後に解決してくれるから面白いのであって、翻訳のミステリーなどは少しも面白くない。頑張っていただいた翻訳会社さんには申し訳ないのだが、すべて自分でリライトさせてもらった。 「翻訳とは何か」といった議論をすると、人それぞれ定義が違うのでキリがないが、筆者個人の定義は、アウトプットされたものが意味をきちんと伝えているのは当然で、ライティングとしてスムーズに読めるものということであり、これは絶対に譲れない。「そこまでの翻訳は期待していません。縦のものが横になっていたら(または横が縦)良いんです」とか、「多少読みにくくても意味が正しく伝わっていればいい」といったお客さんがいれば(幸い、これまでそういうお客さんにはお会いしたことがない)、筆者としては2通りのやり方がある。1つは、そういうお客さんは翻訳料金にも超安価を要求して来られる場合が多いので丁重にお断りする、2つ目は、翻訳料金が通常の価格である場合、やはり、ビジネスとして考えるならばとりあえず受注して、そこそこの品質で料金もお手頃な翻訳会社にすべて依頼し、こちらはざっとチェックして提供するという方法である。 会社という組織に帰属して仕事をしている場合、2つめの方法は取らざるを得ないが、いずれにしても、自分では翻訳はやらない。と言って別に格好をつけているわけではない。原文の文章を単純に翻訳先言語の文章に変換するような作業をやっているとヘンな癖がついてしまうもので、知らず知らずのうちに自分の翻訳が単純横展開調になってしまうというリスクがあるからである。これまで何十年もかかって培ってきた「感覚」というものがおかしくなってしまうことで、これは、絶対に避けたい。 まさに、「翻訳」と言っても、世の中にあふれている「翻訳」にはいろんなスタイルがある。もちろん、良いもの、悪いものを含めてのことだ。失礼かもしれないが「これでお金もらったら、やっぱヤバイでしょう」といったものから、水面をするすると滑っていくようなアイススケート感覚のもの、読む人が小学校レベルならいいかもといった簡単すぎる文章表現のもの、ソース言語とミラー構造をなしているような「左右対称」のもの、一文によくここまで情報を詰め込めると感心してしまうような「ジグゾーパズル型」のもの、骨子となる情報やメッセージをつかんで見事に翻訳先の言語の構造・感覚で表現されているものなどさまざまである。 筆者が評価しているのはもちろん、最後のスタイルだけであり、めざしているのもこのスタイルである。「翻訳の定義」を云々するつもりはないが、筆者個人としての独断と偏見を述べるならば、この最後のものが、スタイルなどを分類するまでもなく、翻訳としてあるべき姿だと考えている。しかし、実際に、この最後の翻訳を提供できる翻訳会社は、筆者の知る限りでは極端に少ない。まあ、翻訳会社100社を使って仕事していますというわけでもないので(そんな必要性もない)、世界が狭いと言われればそれまでだが。 最初の「これでお金もらったら…」というのは、言うまでもなく、誤訳・迷訳の類いであり、先に挙げた「ミステリー翻訳劇場」もこれに該当する。英語の決まり表現なども正しく理解されていなかったり、業界としての常識を理解していないと考えられるレベルで、(翻訳者にとっての)暗号を別の言語の暗号に移し変えている作業である。翻訳先言語の文章表現力の問題に入る前に、外国語としての知識が浅い場合も多く、いろんな意味でプロとして一人で翻訳をするのはとりあえず「待った」ほうがいいのではないかと思われるレベルである。また、細かいことは苦手だとか、めんどうくさいなど、翻訳者として適性的に向いていない場合もあるかもしれない。 次に、「アイススケート型」だが、これは、日本語から英語に翻訳されたと思われるある書籍を読んでつくづく感じたことである。日本における英語教育の歴史について書かれた本で、たまたま古本屋めぐりをしていて見つけた。内容が興味あるものだったことと、古本なので購入価格と内容のバランスといったリスクも少ないので「ま、いいか」ということで入手しておいた本である。英語で書かれたものを読む場合は、やはり、文章の上手いネイティブによって書かれたものを読まなければ意味がないので、情報だけをつかむというつもりで読もうと決め、さっそく読み始めた。しかし、その翻訳内容は、想像していたよりひどいものだった。 随所にある単語のスペルミスもさることながら、英語の読み物として、こういった内容が来ると次にその答えとなる情報が来るはず、という基本的な要求が満たされない。そろそろ具体的な情報(答え)が出てくるかな、と何度も期待するのだがその度に裏切られる。つまり、表面的な情報だけが続き、いつまで経っても核心に触れないのだ。どうしてこういうことになるのだろう、といろいろ考えたが、おそらく日本語の情報をそのまま移し変えているのが原因だろうと思われる。原文となる日本語がわからないので想像の域を出ないが、日本語ならこういった表面的な表現をするだろう(それでいて不自然ではないのが日本語)ということでうなずける。しかし、英語の文章表現なら、もっと具体的な、厳密な情報の定義がなされていないとかなり欲求不満状態に陥る。翻訳者のプロフィールを見ると「同時通訳」の経歴があった。なるほど、あまり考える時間もなくその場で言葉を発していかなければならない同時通訳の手法で翻訳されているような気がした。 誤解のないように言っておくが、同時通訳イコール表面的表現というつもりはない。同時通訳は瞬間芸のようなもので、ソース言語の流れに追従していく必要があるので、行間に隠れた部分を訳出していく余裕などはない。それに、ソース言語が話されているその場の雰囲気や状況などもあるので、ある程度表面的な表現であっても十分通じるのだと思う。しかし、ソース言語の雰囲気やその場の状況から独立した「文章オンリー」の世界では全く事情は異なってくる。ターゲット言語の世界のなかで表現していかないと違和感が発生し、その違和感は読み物としてはかなりストレスがたまるものとなる。もちろん、それ以来、その書籍は部屋のどこかで埃をかぶっている。 次に「左右対称型」と「ジグゾーパズル型」であるが、これはこれでゲームとしては面白い。もちろん、文章としては感心しないし、個人的には良い翻訳としては認められないが、ある種の努力を感じるものでもある。これらのスタイルの根底にあるのは、文章単位、単語単位での移し変えが徹底されており、学校で教えるところの「英作文」などもこれに近いのではないかと思われる。原文で長い文章は翻訳先言語でも長く、短いものは短く、「、」があればコンマを、「。」があればピリオド、「〜があります」とあれば必ず、there is (are)、「これは〜です」とあれば、必ず this is...という表現になり、それ以外は考えられないという世界である。「ジグゾーパズル型」になると、原文が1文ならば、翻訳先言語でも絶対に1文にするという徹底ぶりがある。 日本語は漢字がふんだんに使えるので、比較的短い文章でもいろんな修飾語的な情報を盛り込める。しかし、英語では、漢字2文字が平気で5ワードにも6ワードにもなる場合がある。それを日本語と同様に1文ですまそうとすると、当然、関係代名詞や関係副詞などを使った従属する文章や句が増えてくる。あるコアとなる情報の前や後ろに which....だの、 when...や if...などを目いっぱい引き連れて見事1文に納めるというテクニックはそれはそれで、すごいものがあるのだろうが、読んでいる側にすれば複雑すぎて頭が痛くなる。1文を読むのに何度も前の部分に戻ったりして、どの部分がどの部分にかかっているのだか、学校時代にやったように、 which 節などをカッコで囲んでみたりして、まさにパズルを解読する作業が必要なのである。ひょっとすると、こういった翻訳をしている人は、文章単位、単語単位で言語を移し変えることが忠実に訳すことであり、質の高い翻訳だと考えているのではないかとも思われる。そういう人が、前述の最後のタイプのような翻訳を見ると、「正確に翻訳されていないのではないか」とか「原文を離れて創作してしまっている」といった感じを受けるのかもしれない。 「翻訳」がソース言語からターゲット言語への転換ということであるならば、上記のような意見も出てくるのは当然であり、そういった意味で「翻訳とは何か」といった議論に入るとややこしいのである。筆者としては、「翻訳とは何か」という定義は勝手にそれぞれ判断すればいいことで、要は、まず、スムーズに読めて、欲しい情報が手に入ることが一番というのが自分自身の翻訳に対するニーズである。学生時代に読まされたテキストなどにも外国語から日本語へ翻訳されたものが多く、読むだけでも頭が痛くなった経験がある。当時は、このテーマはこんなに難解なものなのかと思っていたが、今にして思えば、翻訳に文章の工夫がないからあんな肩の凝る文章になっていたに違いないと確信している。 パズルがしたければパズルをすればいいのであって、何も難解な文章を解読する必要はない。少なくとも筆者にはそんな根性はない。たとえ興味のある内容であっても、小難しい文章で書かれた書籍などは絶対に買わない、読まない。だから、自分が翻訳するとしたら、自分にとって理解しやすい表現をするというのはごく自然なことなのである。(もちろん、ここで言うわかりやすい表現とは、小学生のようなジュニアレベルのことを言うのではない。)こんなことを言うと、アカデミックな世界のエライ先生方に「オマエはむずかしい文章が読めないただのアホ」と言われるかもしれないが、それでもいい、難解な文章はありがたくも何ともないし、第一、難解なものを平易に表現できないというのでは「先生」はつとまらないわけである。特に、企業から発信する情報(翻訳)などには、一般の人が読んでもわかりやすいということに最も高いプライオリティが置かれる。なかでも機械の操作マニュアルなど、使い方を間違えば事故にもつながるような情報には、いろんな学力レベルの人が読んでも簡単に理解できるようなさまざまな工夫がされている。  ということで、最後のスタイルである。これは、一言で言えば、翻訳すると同時にアウトプットがライティングとしても耐えうるものになっているということだ。くどいようだが、ライティングと言っても、「当機械本体の電源が投入されている場合においてのみ、機械の操作モードが手動ではなく自動に設定されている際、また、○○タイプのインターフェースを使用している場合はこの限りではないが、本体の底にあるカバーを赤いレバーを使用して開いた場合に観察されるところのホルダーに格納されている右側のスイッチを押すことで、自動診断機能が稼動を開始します」といったミステリー・パズル的な文章や、「電気を入れるスイッチは機械の底の部分にあります。機械を裏返してください。そうすれば、そこにスイッチがあるのをあなたは見るでしょう」といった稚拙かつ直訳的な表現を言うのではない。あくまでも、用途や読者に応じて、読みやすい、わかりやすい文章ということである。
ということで、最後のスタイルである。これは、一言で言えば、翻訳すると同時にアウトプットがライティングとしても耐えうるものになっているということだ。くどいようだが、ライティングと言っても、「当機械本体の電源が投入されている場合においてのみ、機械の操作モードが手動ではなく自動に設定されている際、また、○○タイプのインターフェースを使用している場合はこの限りではないが、本体の底にあるカバーを赤いレバーを使用して開いた場合に観察されるところのホルダーに格納されている右側のスイッチを押すことで、自動診断機能が稼動を開始します」といったミステリー・パズル的な文章や、「電気を入れるスイッチは機械の底の部分にあります。機械を裏返してください。そうすれば、そこにスイッチがあるのをあなたは見るでしょう」といった稚拙かつ直訳的な表現を言うのではない。あくまでも、用途や読者に応じて、読みやすい、わかりやすい文章ということである。だいたい日本語がわかるからといって誰でも優れた日本語の文章が書けるわけでもなく、英語がわかるからといって優れた英語の文章が書けるとは限らない。それじゃ、何のために「プロ」が要るのかということになる。このスタイルの翻訳を提供するためには、かなりの技量や力量が要求される。まず、第一に原文と翻訳先の言語についての深い理解と知識が必要である。日英翻訳の場合、英語を理解しているのはもちろん、日本語に対するきちんとした知識も必要で、「馬から落馬しました」とか「全然大丈夫です」といった表現を違和感なく使っているようでは不安だ。もっとも、言葉というものは変化するもので、そのうち「全然」の後にも否定だけではなく「肯定的」な内容が来るような使い方も一般的になってしまうかもしれないが、あくまでも現代において、一般的に受け入れられる正しい表現ができるという必要がある。第二に、扱っている分野の十分な知識を持っているということである。金融、医学、食品、生産技術などいろんな分野があるが、それぞれの分野の知識や事情を理解していなければならない。 これがないと、ミステリー的な翻訳になりやすく、また、ターゲット言語の表現特性に合わせて思い切った表現ができないということになる。第三に、文章や単語ユニットに関わらず、情報・メッセージとして原文をとらえ、とらえたものを翻訳先言語の感覚や構造で表現できるかということだ。この第三のポイントは非常に説明しにくいものだが、最も高いハードルである。サービス精神とか、創造力、感性に左右される部分が多く、人によって向き不向きの部分もあるからだ。場合によって、原文では省略されている修飾語を入れたり、逆に「言わずもがな」の部分を省いたりする。また、状況や文脈に応じて、異なる情報に置き換えることもある。これは、その商品・サービス、業界などの知識がないとできない。原文で省かれているものが「どこの何の部分」なのかといったことが知識なしでは推測できないわけである。 こういった翻訳のスタイルは、機械翻訳などの手法ではとうてい対応できない。まさに、職人芸である。生産現場でも昔は職人芸と言われていたことが、今ではコンピュータを使った自動制御によって置き換えられる時代になってきたが、翻訳はそういうわけにはいかない。生産技術の発展の背景には、それまで「ブラックボックス化」していた個人のノウハウ、「さじ加減」というようなものを数値化するといった目に見える形で表現できるようになったという事実がある。しかし、「良い翻訳」と言っても一通りではなく、何通りもの表現が可能だ。また、その人の感覚、経験、発想、思考回路、心理、などありとあらゆる目に見えない要素が複雑に絡み合い、ある種「偶然」とも言えるような形で出てくるものであるため、それを数値化し、制御するというのは不可能に近いものがある。少なくとも、人間の脳の動きが具体的に数値化され、どういう働きのときにこういった発想がなされ、背景にこのような経験則がある場合に、このような翻訳表現としてアウトプットされるということが「数値で見える」ようになるまでは実現することはないだろう。 以上のような理由から、筆者の考える「質の高い翻訳」というのは、膨大なエネルギーや手間がかかるものであり、大げさな言い方をすれば、翻訳者の頭脳の働きに大きく左右されるものである。よって、今日は何千ワード処理しましたといった「処理」の部分もあるが、それ以上に、2つの言語の世界を行き来しながら「言葉をつむいでいく」ような行為だという気がしている。しかし、有名画家の絵1枚が何千万円といった芸術の世界ではないので、この翻訳1ページ10万円です、というわけにはいかない。翻訳というものの位置付けはあくまでも、原文の作品や商品・サービスの付随物であり、それ自体で存在するものではないため、高い経済価値をつけられない性質のものである。その反面、翻訳者の持っている人的リソースを多いに活用する必要があり、結局、筆者の考える質の高い翻訳を提供しようとすれば、ビジネスとして成立しないのである。「質の高い」の範囲をどこまでにするか、意味が通っていて、用語の統一ができていれば良しとしようといった妥協をせざるを得ないのも現状である。 しかし、企業のビジネスとしては採算が合わない仕事であるが、個人レベルではなんとか食べていけないこともない。例えば、20ページ程度の企業パンフレットで10万円くらいの売上になるとする。その業界について知識を得るための準備が1日、実際の翻訳作業が3日、ネイティブチェックなどをして最終的にデータを整理するのが1日として、だいたい4日とする。個人レベルならこういった仕事が月に4本もあり、その合間に小さい仕事をちょこちょこやると、それほど贅沢はできないにしても、まあまあ食べていける。これが、会社に所属している社員となるとちょっときつい。会社としては一人の正社員についていろんなコストがかかるものであり、一般には、給料の2倍から3倍利益を上げなければ商売にならない。よって、翻訳者を社員として抱えるのではなく、外注スタッフのような扱いで、どんどん受注してどんどん仕事を出し、翻訳者に支払う翻訳料金の上に何がしかを乗せたものを利益として計上するというビジネスモデルが伝統的だ。数をこなして幾らの世界なので、品質はある程度のところで線引きされることになる。 というようなことから、「翻訳」という仕事をフルにエンジョイするためには、個人の翻訳者として仕事をするほうが効率も良く、質の高いものができる。というようなこともあって、筆者もフリーになろうと決心した。幅広く社会経験をする時代もそろそろ終わりにし、会社の看板から離れて個人でやってみたいという気運が高まってきたのである。今の会社には16年も在籍していたが、会社という組織上、翻訳以外の業務もやらざるをえない状況もあり、いろんな経験をさせてもらった。その集大成として、今後は翻訳を始めとする、英語・語学関連の分野で仕事の花を咲かせたいということである。セレブになるとか、大金を稼ぎたいといったことではない。これまでの経験をブレンドして、好きな翻訳の分野を仕事の中心におきながら、自分自身に納得できる「花」の咲き方である。やはり自分の好きなことをしているのが一番楽しいし、楽しいことをやりながら食べていける、そんな時代が来たのではないかと思うのである。 ということで、昨年の9月、決意も新たに「退職願」なるものを手に社長室へと向ったのである。厳しい世の中の状況でもあるし、あまり売上の規模に貢献することのない翻訳業務を中心にやってきた社員が一人辞めたとしても、会社にとってはむしろ望ましいことだろうし、儀礼的な「待った」がかかったとしても最終的にはこれで円満退社だと確信していた。しかし、予想に反して社長の反応は「ショック」だったらしい。何を隠そう、ウチの会社というのは人情的な会社なのである。小さな会社ということもあり、外国語を理解する人間は筆者のみで、その意味でも大切にしてもらった。おまけに社長には仲人もやってもらったりで個人的にお世話になっている。一般的な意味でのキャリアを積むという点では、物足りない部分もあるが、筆者も16年もいたということはそれなりに居心地のよい会社であることには違いない。そこまで止めてもらうほどの人材ではないのに… と思うし、会社としても、自分のような人間は外注スタッフとして使ったほうが効率がいいのにとも思うが、ショックを受けておられる社長の態度にこちらもショックを受けたような感じで、その日はとりあえず「保留」ということにして、後日、話し合いを持つことにした。 そして、1週間後、再度話し合いを持ち、こちらとしても1年間考えた末の結論でもあることから、両者の間を取って、とりあえず「契約社員」として籍を置くことにし、自宅勤務という条件も承諾してもらった。半分フリーのような形である。保証の部分も減らしてもらう代わりに、会社に関係ない仕事も行ってもよいということになっている。とは言え、現在のところ、会社からの仕事が続いており、自分から営業に回っているヒマもない(たぶん営業回りのようなやり方はしないと思うが)。しかし、おかげで、長年行けなかった歯医者にもじっくり通うことができるし、仕事をしていて、眠いと思えばその場でごろんと横になれる。その代わり、勤務時間に関係なく、急ぎの仕事なら徹夜もするし、私用でちょっとお出かけという場合にも、携帯で呼び出されて自宅に呼び戻される場合もある。本来、場所や時間に縛られるのが苦手で、大学卒業後もフリースタイルのような働き方をしたいと思っていたが、そんな時代でもなく、長年会社勤務をしてきた。しかし、いよいよ、21世紀になり、自分のスタイルで自分の好きなことをやって生きていける時代だ!と痛感している(のは筆者だけかもしれないが)。 いずれにしろ、しばらくは、会社の好意に甘えて半分フリーのライフスタイルを楽しみながら、自分のめざす翻訳のスタイルの可能性を追及していきたいと思う。いろんな業種の翻訳を手がけることでその分野のことを知ることができるというのも面白い。それぞれの世界にはそれぞれの技術や経験、知識や智恵があり、準備のための調査をするたびにわくわくする。やはり、未知のことにチャレンジするのは楽しいものである。 |
|
|
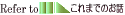 |










