
|
| se の歴史的考察2 |
|
| 与格代名詞の se | 再帰代名詞三人称の se |
|
再帰代名詞3人称の se
上の項で、ラテン語には3人称代名詞は存在しなかったということを述べましたが、唯一、3人称代名詞として存在していたのが再帰代名詞です。このラテン語の再帰代名詞3人称がスペイン語の再帰代名詞3人称の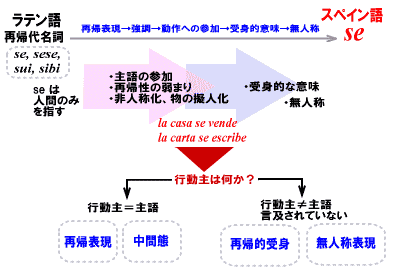
スペイン語の受動態の考え方の歴史的考察でも述べていますが、すでにラテン語の時代から、再帰代名詞を使った用例には、中間態と呼ばれる、再帰表現以外のものが存在していました。
「自分自身を~する」という場合の「自分自身」を表す代名詞が再帰代名詞ですが、「再帰」とは主語自身に動作の影響が跳ね返ってくるため、主語に「動作の影響が及ぶ範囲に参加させる」という働きを持っていると言えます。ところが、「動作の影響」というものは、その動詞の種類や意味によっても異なってきます。再帰代名詞がいろんな動詞と組み合わせて使用されるうちに、その働きがだんだんと拡大・変化し、自動詞的な表現や受身に近い意味へと発展していったと考えることができます。つまり、中間態、再帰的受身、無人称表現といった用例が生み出されたわけです。
主語が自分以外の目的語に対して、目に見える動きのあるアクションを及ぼす動詞が最もアクティブな動詞であると考えることができます。言い換えれば、動作の方向が外側に向いている動詞ということですが、こういった動詞が主語自身に対して使われる場合に再帰表現となります。一方、主語自身の状態や性質などを表す静的な(内側に向いた)動詞もあります。このような動詞と再帰代名詞が組み合わされると、再帰代名詞の「再帰性」が弱まり、動作の影響範囲への参加のみがクルーズアップされる中間態の用例へと移行していきます。さらに、その中間態としての用例のなかには、動詞の種類や語順、時制などにより、意味的には受身に近いと思われるものも現れ、そこから再帰的受身の用例へと発展したということが言えます。
また、もともとは人間にしか使われなかった再帰代名詞の
|
↓ ↓ |
いずれにしろ、中間態から受身への移行は、単純に図式化できるものではなく、さまざまな要素が絡み合い、現在の形になったようです。また、「これが中間態、あるいは受身」といった文体の違いが明確ではないため、脈絡で判断するしかないのですが、ざっくりとした目安として、「行動主が主語である場合は再帰・中間態」であり、逆に、「行動主が主語でない場合は受動態」ということが言えるでしょう。
|
| 与格代名詞の se | 再帰代名詞三人称の se |
|










